環境法規制 規制の概略と実務知識 (全5回)
技術系研修
- その他
環境法の全体像を学び、個別の法規制と対応実務を深く理解する
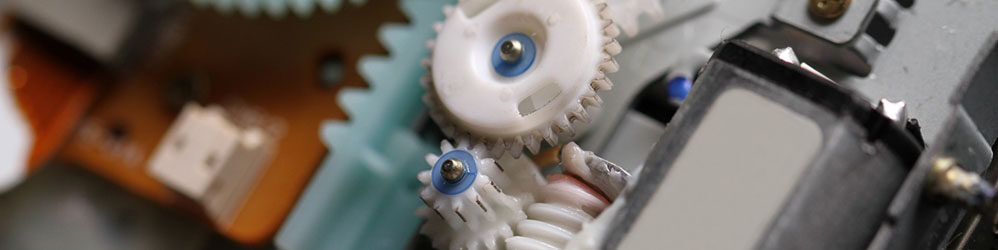
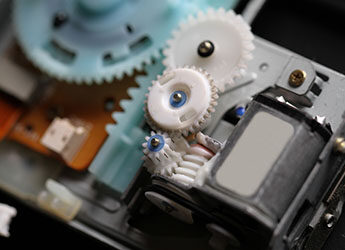
セミナー内容
-
各回のタイトルをクリックすると、単発の申込ページへアクセスできます
- ◎こんな形での受講がおススメ!
-
《テーマ①》+《テーマ②~⑤のうち自社に関係するテーマ》
テーマ①で各種法令の種類と対象範囲を学び、テーマ②~⑤で自社が関係する法令の具体的な規制基準値や法令対応実務を個別で学ぶことで、理解が深まります。もちろん各テーマを単独で受講することも可能です。
環境管理活動で第一に考えるべきは、自社の事業内容に該当する環境法規制を特定し、遵守することです。しかし法令はどれも難解で、頻繁に行われる改訂や規制強化への対応にも大変苦慮します。そこでこの「環境法規制」セミナーパッケージでは、自社がどの法規制の対象にあたるのかを整理する2日間セミナーと、各法規制の基準値の詳細や具体的な実務内容を学ぶ1日セミナーを用意しています。2日間セミナーの受講後に各法規制の個別セミナーを受講いただくことで理解がクリアなものとなり、実務にいかせる体系的知識が身につきます。環境法に対する知見の豊かな担当者育成のために、ぜひ本セミナーをご活用ください。
- テーマ①環境法規制の全体像(2日間) 2025年6月10日(火)・11日(水)
-
1.“法令”てなに?から理解する環境法の基礎
●環境関連法の法体系
●法律、施行令、省令… etc.
●環境法令と環境マネジメントシステムの関連性
-ISO14001とエコアクション21
2.“環境基本法”と政府の方針
●法体系全体における環境基本法の立ち位置
●環境基本法が定める事業者の責務
●政府の方針と今後の展望
3.“公害防止”のための規制と事業者の責務
●環境基本法における「公害」の定義
●“特定工場”にあたる業種と“公害防止組織”とは?
●法律に求められる事業者の責務
●自社の工場配置を法規制に照らし合わせてみよう
4.各種公害に関わる法規制
●“水質汚濁”にかかわる法規制と規制対象
-水質汚濁防止法、下水道法、浄化槽法 など
●“大気汚染”にかかわる法規制と規制対象
-大気汚染防止法 など
●“騒音・振動”にかかわる法規制と規制対象
-騒音規制法、振動防止法 など
●“土壌汚染”にかかわる法規制と規制対象
-土壌汚染対策法 など
●“地盤沈下”にかかわる法規制と規制対象
-工業用水法 など
●“悪臭”にかかわる法規制と規制対象
-悪臭防止法 など
5.化学物質の取扱いに関する法規制
●特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)
●化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
●毒物及び劇物取締法
●消防法(危険物関連)
●労働安全衛生法(有機則、特化則、粉じん則)
6.循環型社会構築に関する法規制
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
●3Rに関する法律
-循環型社会形成推進基本法 など
●エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)
●各種リサイクルに関する法律
-家電リサイクル法、 食品リサイクル法 など
7.その他の知っておきたい環境関連規制
●フロン排出抑制法
●自動車の排ガスに関する法規制
-自動車NOⅹ・PM法、オフロード法 など
●気をつけておきたい“光害対策ガイドライン”
●多くの事業者が関わる海外の環境関連の概要
-RoHS指令、WEEE規制、REACH規則
8.環境法関連の情報収集
●知っておきたい環境法令に関する最新動向
●有用な情報リソースを紹介
- テーマ②排水の規制基準と処理技術 2025年7月18日(金)
-
1.世の中の水の流れと各法令の目的
●はじめに知っておきたい世の中の水の循環
●水質関連の各法律の目的とその背景
-水質汚濁防止法、浄化槽法、下水道法 など
2.基本法令における排水に関する規制内容
●環境基本法が定める水質関係の環境基準
●特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止組織法)が定める事業者の義務
3.水質汚濁防止法の規制内容
●水濁法における「排水基準」と「上乗せ基準」
●事業者に課せられる責務
●違反時の罰則
4.下水道法、浄化槽法、その他の規制内容
●下水道法-基準値と測定に関する義務
●浄化槽法-浄化槽管理者の設置義務と法定検査
●土壌汚染対策法、工業用水法(地下水関係)
●さまざまな水の水質に関する基準
5.各種排水処理技術の概略と用途
●物理的・化学的処理のメカニズムと用途
-ろ過、凝集沈殿、イオン交換、活性炭吸着 など
●生物的処理のメカニズムと用途
-活性汚泥法、生物膜法、嫌気性/好気性処理法 など
6.排水処理技術を応用した工場の節水事例
●排水の再利用により水使用量を低減した事例を紹介
- テーマ③産業廃棄物の規制と管理実務 2025年8月28日(木)
-
1.廃棄物処理法における事業者の責務
●廃棄物処理法の違反リスク
●排出事業者に課せられる義務
●産業廃棄物の区別と区分
2.処理委託先を選定する際のポイント
●処理業者へ処理委託を依頼するまでの流れ
●処理業者の信頼性を確認する際のポイント
●処理業者へ実施確認をする際のポイント
3.委託契約締結に関するポイント
●契約締結の6つのポイント
●委託契約書の記載事項と取扱いに関する義務
●委託契約のリスクを最小化するには?
●【演習】収集運搬委託契約書の不備を指摘してみよう
4.マニフェスト作成のポイント
●マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは?
●マニフェストの交付から保管・報告までの手順
●マニフェストが返送された際のポイント
●電子マニフェストの注意点
●【演習】マニフェストの間違い探し
5.委託先への監査の進め方
●監査を行うために準備すべきもの
●収集運搬業者への監査ポイント
●処分業者への監査ポイント
- テーマ④化学物質の規制と安全管理 2025年9月19日(金)
-
1.化学物質に関する法令と行政の動向
●過去に発生した事故・事件に学ぶ
●カテゴリー別 化学物質に関わる法令の概観
-環境保全、労働安全、防災保安、リスク管理
2.法令が定める事業者の責務
●PRTR法-排出量の把握・届出、SDSの提供
●化審法-新規化学物質の審査、各種届出
●労働安全衛生法-GHS絵表示、リスクアセスメント
●消防法-危険物の取扱い、各種届出・義務
●毒劇物取締法-登録・許可の義務、その他の義務
3.化学物質の安全管理体制構築
●管理の失敗事例
●安全管理の目標設定と目標管理
●定期的なリスク管理で不安全を未然防止
●法令順守に向けたチェックリストの作成
●目標に対するマネジメントレビューのポイント
●管理体制の維持更新に向けた情報収集の進め方
4.現場のコンプライアンス意識を高めるには?
●現場で起きやすいプチ法令違反
●分かりやすいマニュアル作成のポイント
●化学物質関連法への理解を高める社内教育の実践
- テーマ⑤騒音・振動の規制と低減策 2025年10月15日(水)
-
1.騒音・振動の法律での規制内容
●騒音規制法に定められる規制の理解
●国が定める騒音防止のガイドライン
●振動規制法に定められる規制の理解
●振動の種類と対策が必要となる場面
2.騒音・振動の規制基準値と測定方法
●騒音・振動に関する数値の意味と基準値の理解
●騒音・振動の測定方法と発生源の見つけ方
●【演習】対策立案に必要な“周波数分析”のやり方
3.工場で行う騒音対策の進め方
●騒音対策の2つのカギ 「吸音」「遮音」
●吸音材の特性とその効果
●遮音材の特性とその効果
●騒音対策の実際の事例
4.工場で行う振動対策の進め方
●振動対策の定石は“ばね-マス系”
●対策効果の予測をやってみよう
●振動対策の実際の事例
- 受講費について
-
●テーマ①のみ
会員会社 ¥44,550/非会員会社 ¥56,650
●テーマ②~⑤ 1テーマにつき
会員会社 ¥29,150/非会員会社 ¥35,200
●テーマ①+テーマ②~⑤のいずれかひとつ(セット受講)
会員会社 ¥62,700/非会員会社 ¥80,410
※セット受講に追加で受講される場合 追加1テーマにつき
会員会社 ¥18,150 /非会員会社 ¥23,760
※いずれも消費税10%込み
※すべて1名あたりの金額です
セミナー要項
| 名称 | 環境法規制 規制の概略と実務知識 (全5回) |
|---|---|
| 開催場所 | 大阪府工業協会 研修室 |
| 価格(税込み) | 62,700円(会員)/80,410円(非会員)●テーマ①+テーマ②~⑤のいずれかひとつ(セット受講)/その他の組み合わせについてはセミナー内容欄【受講費について】をご確認ください |
開催日・開催予定日
| 2025年6月10日(火)から2025年10月15日(水) | 午前9時45分~午後4時45分 |
|---|
関連するセミナー
